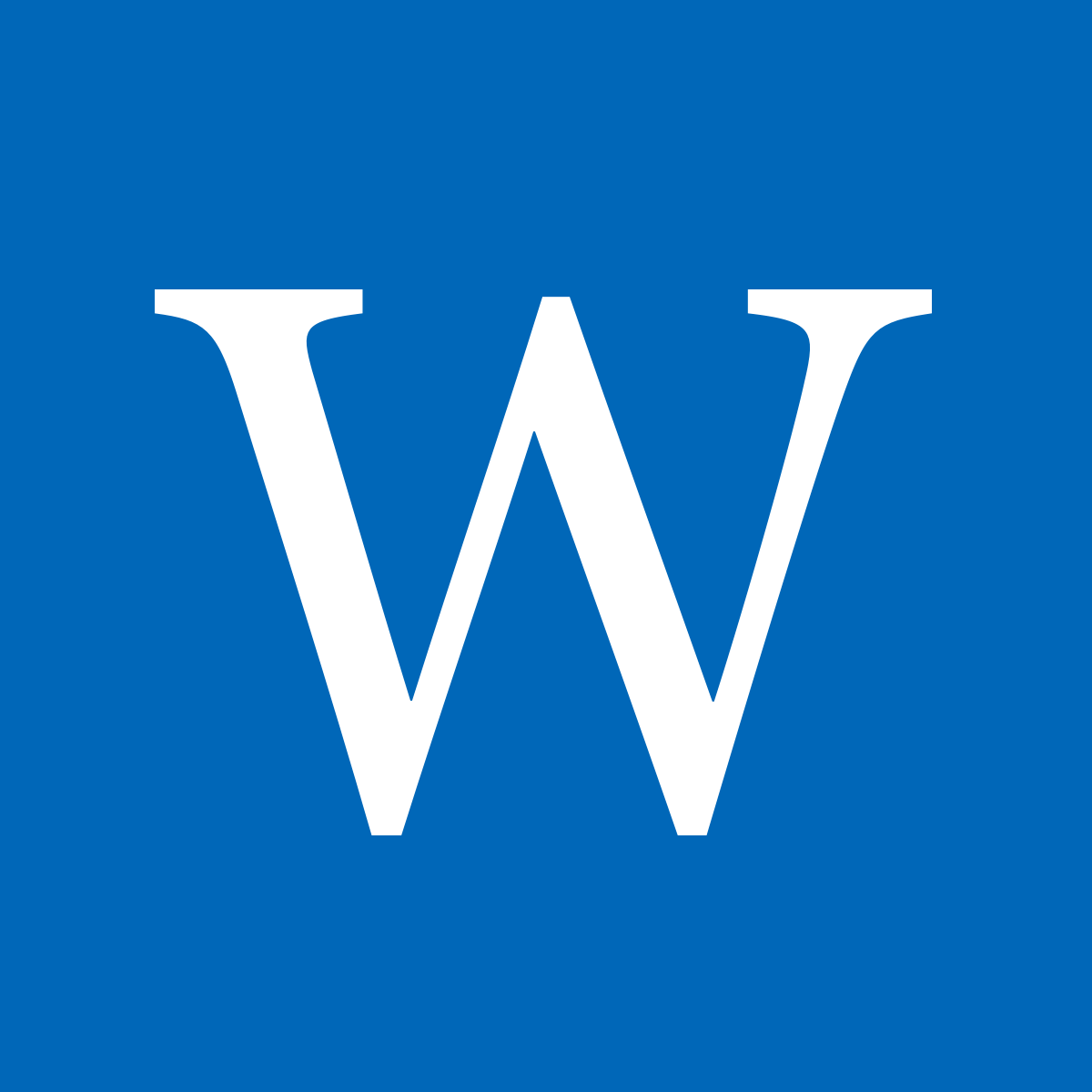日本の醸造所は創意工夫を凝らし、日本酒製品にフルーツやその他の材料の香りや風味を加えて、いわゆる「クラフト日本酒」を生み出しています。 この革新的なアプローチにより、醸造所ライセンスの取得と新しい市場への参入が容易になります。
若い醸造家は、国際的に販売することを目的とした職人技の日本酒製品を開発することが特に目立っています。 しかし、彼らはまず自分たちの作品を国内市場に押し出したいと考えています。 伝統的な日本酒は、米と麹菌を原料として発酵させ、圧搾して液体を作ります。
簡単なライセンスと新しいフレーバー
地酒は酒税法上「その他の醸造酒」に分類されます。 その理由は、これらの醸造所が伝統的な日本酒では許可されていない果物やその他の材料を使用しているためです。 「その他の醸造酒」は清酒の免許よりも取得が容易です。
クラフト日本酒の概念は、2022年に7社で設立された全国地酒協会によって導入された。同協会の会長は、秋田県の株式会社伊根とリュウゼツラン醸造所の岡住修平社長である。
革新的なビール醸造所とその製品
「いねとリュウゼツラン」は、男鹿半島のJR男鹿駅近くの古い駅舎で2021年に誕生しました。 20 人の従業員からなるチームは、ホップやその他の原料から独特の風味を引き出した、ナツメグのような酒を職人技で製造しています。 岡積氏は、伝統的な米酒では使用できない原料を使用できるため、職人酒の多用途性を強調します。
「伊根とリュウゼツラン」では伝統的な食材に加え、リンゴやブドウ、粕を取り除いていない「どぶろく」の生酒なども試作している。 この醸造所では年間 40,000 リットルの日本酒が生産されています。
市場の課題と可能性
日本では売り上げ不振や倒産回避のため、半世紀以上にわたり新酒の醸造免許が制限されてきた。 そのため、岡住さんは酒業界への参入が難しくなり、酒造りの道へ転向した。
東京地酒醸造協会のもう一つの会員である木花野酒造は、年間 7,000 リットルの桃酒やその他の飲料を生産しています。 この醸造所は、クラフトビールと同様に、醸造所、レストラン、顧客の間に密接なつながりを築くことを目指しています。
国際的なビジョンと今後のプロジェクト
日本酒イベントへの協会会員の招待も増えており、協会商品の人気が高まっていることがわかります。 しかし、地酒市場は依然として比較的小さい。 岡積は、クラフト日本酒の価格を伝統的な日本酒のレベルに引き上げるために、生産量を10倍に増やす計画を立てている。
木花野酒造は最近シンガポールに施設を開設し、福岡を拠点とするリブロムクラフト酒造は中国、台湾、香港への輸出を増やしている。 醸造酒は海外でより容易に受け入れられ、世界市場を征服できる可能性があります。
原料に制限のない米国や欧州を中心に海外の酒造メーカーも増えている。 岡積氏は、職人の日本酒が寿司と同じように世界中で成功し、海外での日本酒の消費拡大に貢献することを期待している。

「熱心なトラブルメーカー。アマチュア旅行の第一人者。熱心なアルコール愛好家。ゾンビ学者。」